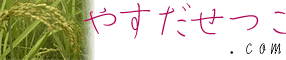�V���g�݊����C�l�i�ō��قւ̍R�����R
�͂��߂�
�g�݊����C�l�̖�O�͔|�����~�߉������i�ׂ͍ō��ق֏㍐���܂����B���̍R�����R����10��4���ɒ�o���܂����B���̍ٔ��̈Ӗ�����Ƃ��낪�����Ɏw�E����Ă��܂��B
�l�H�I�ɏ펞�R�ە����傷��g�݊����C�l���ϐ��a���ۂ��o��������\���������A�����Ȃ����ꍇ�A�l�ނ͂��Ƃ�萶�Ԍn�A���ɋy�ڂ��j��I�e�����뜜�����Ɛ��Ƃ��͂�����Ǝw�E���Ă��܂��B
�����q�v�ٌ�m�ɂ�鐸�����߂����͂����Гǂ�ł��������B���̍ٔ��̓��e�ƈӋ`���M���v���ƂƂ��ɖ����ɓ`����Ă���͂��ł�
�R�����R��
����17�N�i���N�j��561�� �\���l�@�R�c���@�O11�� ������@�Ɨ��s���@�l�_�ƁE�����n����Y�ƋZ�p�����@�\���ʍR�����R��
2005�N11��4��
���������ٔ�����5�������@�䒆
�\���l��㗝�l
�ٌ�m�@�_�R���q�q
���@���ؗ���
���@���O�K��
���@�ߓ���j
���@�n��G�s
���@�����q�v
���������̍R�����R�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�ڎ�
1�A�\���l�����ʍR���ɋy���R�@2�� 2�A���@�ᔽ�̈Ӗ��ɂ��ā@3�� 3�A�͂��߂Ɂ\�\�\���l�ɂƂ��ė\�z�O�̏o�����\�\�@4�� 4�A�{�ٔ��̎��@5�� 5�A�{�ٔ��̑��_�𖾂ƍR���R�̐R���o�߁@6�� 6�A�{GM�C�l�ƈ�ʃC�l�ƌ��G�̉\���@7�� 7�A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���Ƃ��̉e���@9�� 8�A��O�������F�̂��߂̐\���i�K�ɂ�����d��Ȏ葱�ᔽ�@12�� 9�A���f��Ƃ��Ắu�\�h�����v�̕K�v���@14�� 10�A�R���̎�|�ύX�̉ۂɂ��ā@15�� 11�A�I���Ɂ\�\�������܂ꂴ��҂����ɑ���`���̗��s�\�\�@17��
1�A�\���l�����ʍR���ɋy���R
�����܂ł��Ȃ��A�\���l���{���ōł��뜜���Ă�܂Ȃ����Ƃ́A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���E���o�ɂ��l�ނ��̑����A���ɋy�ڂ��d�傩�[���ȉe���i���N��Q�A���Ԍn�̔j��j�ɑ��A���̂悤�ȏd��ȐN�Q�����Ɍ��N�ŕ����I�Ȑ������c�ތ��������@��ۏႳ��Ă���ɂ��ւ�炸�i���@25���E13���j�A�w�⌤���̎��R�̖��̉��ɁA���@����ł����d����đR��ׂ����̐��������s�\�Ȍ`�ő��Ȃ��Ă��܂����Ƃł���B
���������뜜�������Đ\���l�́u�X�J�v�łȂ����Ƃ́A�������������A�����ɂ����āA����قǓO�ꂵ���\�h����J��Ԃ��Ă����ɂ��ւ�炸�A������������H���~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����肩�A���␢�E�I���s�̌��O�������������Ă����i�f�B�t�F���V���ϐ��ۂƓ��l�̐����ЊQ�ł���j���C���t���G���U�̖҈Ђ�����Ζ��炩�ł���B
�܂��A�ߔN�̑�K�͐H�i���̂̉ߋ��ɂ͌����Ȃ����������ȓ����Ƃ��āA�Љ�q���̑f���炵������ɂ�������炸�AO157�H���ł�BSE�i�����a�j�Ȃǂ̐[���Ȑ����ЊQ���������i�b1�j�A���������̔�Q�̔����A�g��ɁA�{�����H�����̋��Ɏ��S���̃��T�C�N�����p�i�����Ƃ��ē��������g�p�j�̓����Ƃ������o�ό����D��̐l�דI�ȑ���̓������傫����^���Ă���_�ł���B�܂�A����̏d�傩�[���Ȑ����ЊQ�́A���܂����R�����I�ɐ��������̂ł͂Ȃ��A�l�דI�ȑ��삪�������ƂȂ��Ĕ�������\�����ɂ߂č������̂ł��邱�Ƃ����F������Ȃ��B
�����ŁA����������K�͐H�i���̂̋��Ђ̌��ʁA����AO157�H���ł�BSE�i�����a�j�Ȃǂ̔�Q�����Ɍ��N�ŕ����I�Ȑ������c�ނ��Ƃ͌���s���ɂƂ��ċɂ߂Đ؎��ȁA����䂦�ł������I�ȗv���ƂȂ��Ă���A���������āA���ꂪ�A���@25���A��13���ɂ��A�������̐l�i���I���ʁE���R���I���ʂƂ��ĕۏႳ���ׂ����̂ł��邱�Ƃ͌������܂��Ȃ��B
������ɁA���R�ٔ����́A���̓_�̏d�含���܂������ڂ݂Ȃ��܂܁A�w�⌤���̎��R�̖��̉��ɑ�����̈�`�q�g�����i�ȉ��AGM�Ƃ����j�C�l�̖�O������F�߁A���̌��ʁA���@����ł����d����đR��ׂ��������̐N�Q�������炷���@�ᔽ�̌�����������B
�����ŁA�\���l�́A�{�ٔ��Ŗ���Ă����肪�����I�̐l�ނ̐����ɐ[���ւ��ŏd�v�̖��ł��邱�Ƃɂ��݁A���ʍR�����s�Ȃ������̂ł���B
2�A���@�ᔽ�̈Ӗ��ɂ���
�u���ׂč����́A���N�ŕ����I�ȍŒ���x�̐������c�ތ�����L����v���߂����@25���́A�ٔ��ケ��܂ŁA��Ƃ��āu�Œ���x�̐������v�������邽�߂̌o�ϓI�ȕۏ���߂����Ė��ɂȂ������A�������A�������͂��Ƃ��Ƃ��̂悤�Ȍo�ϓI�A���Y�I���ʂ����ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ������B�������Ɋ�Â��u�H�i�q���@�A����{�@�A��C�����h�~�@�Ȃnj��O�q���̂��߂̐��x�̐������}���Ă����v�i�����M��u���@�v�V��239�Łj���Ƃ�������炩�ʂ�A�܂��A1960�N��̍��x�����̌��ʁA��K�͂Ȍ��Q���������A�����������j��钆�ŁA�u���N�ʼn��K�Ȑ������ێ����邽�߂̏����Ƃ��āA�ǂ��������A������x�z���錠���v�i�����j���A�������̈���e�Ƃ��Ď咣�����Ɏ��������Ƃ�������炩�Ȓʂ�A����ɂ́A�����I�ȑn�����ی�Ɋւ����{�@�ł��钘�쌠�@���A���Y�I�Ȍ����i���쌠�j�݂̂Ȃ炸�A�l�i�I�Ȍ����i����Ґl�i���j�����ۏႵ�Ă��邱�Ƃ�������炩�Ȓʂ�A���������܂��A�o�ϓI�A���Y�I���ʂ̕ۏ�݂̂Ȃ炸�A�l�i���I�ȑ��ʂ܂ŕۏႳ��邱�Ƃɂ��A���߂Ă��̖{���̖ړI���B���������̂ł���B�܂�A�s���́A�������̐l�i���I���ʂƂ��āA���N��j��邱�ƂȂ��A�܂���X�̐����̊�Ղł��鐶�Ԍn��j��邱�ƂȂ��A���N�ŕ����I�Ȑ������c�ތ�����L����B�����ɂ���́A���̌����̎�����}�邽�߂ɁA�����͂ɂ��ϋɓI�Ȋ��ۑS�E���P�̂��߂̎{��������͂ɗv������Ƃ����Ӗ��ŎЉ�I�ȑ��ʂ�L����Ƌ��ɁA���N��Q�A���Ԍn�̔j��������炷���҂̌o�ϊ����E�����������K������Ƃ����Ӗ��Ŏ��R���I�ȑ��ʂ�L����i���̈Ӗ��ŁA���@�̑̌n��A13���̍K���Nj����̈���e���Ȃ��ƌ������Ƃ��ł���j�B
�����āA�\���̎��R�������`�Љ�̎����𐧂��A���̍������Ȃ��ɂ߂ďd�v�Ȑl���ł���Ƃ���A���Ԍn��j��邱�ƂȂ����N�ŕ����I�Ȑ������c�ތ����́A���ꂪ����ꂽ�Ƃ��ɂ͐l�ނ̂��ׂĂ̎��R�ƌ��������͂⑶�������Ȃ��Ȃ�قǂ́A�l�ԎЉ�ɂƂ��č������Ȃ��ł��d�v�Ȑl���ł���B
�{���ł́A�u�l�Ԃ̗��j��O��̂Ȃ��Z�p��̗͋Ɓv�ł����`�q�g�����Z�p�Ƃ����l�דI�ȑ���ɂ��A�s���̌��N��Ԍn�ɐ[���ȍЖ�������炷�댯���Ƃ�����肪����Ă���A�܂��ɁA�������̎��R���I�ȑ��ʁA�܂�A�l�ԎЉ�̍������Ȃ��ŏd�v�Ȑ������Ɗw�⌤���̎��R�Ƃ����l�����݂̍ł��[���ȏՓ˂̒���������Ă���A���R�ٔ����́A���̒����̎d���ɂ��āA�u�l���̎����I�����ȕۏ���m�ہv�i�{��r�`�u���@�T�v235�Łj���邱�Ƃ����߂��Ă��錛�@�̉��߂���������̂ł���B
�܂��A10�Ō�q����ʂ�A���R����́A�s�K�ȑi�w���Ɛ\���l��̐\���̎�|�ύX�ɑ��s���Ȑ����������邱�Ƃɂ��A�\���l��̍ٔ����錠���i���@32���j�����N�Q�������̂ł���B
3�A�͂��߂Ɂ\�\�\���l�ɂƂ��ė\�z�O�̏o�����\�\ �����ȂƂ���A��X�\���l��₻�̑㗝�l�ł���S���\�z���Ă��Ȃ��������Ԃ��{�������ٔ���ʂ��ċN�����B����́A�uGM�Z�p�ɏ]������Ȋw�҂�95���͊J�����ɗ����Ă���v�i�b58��NHK-BS�ԑg�̃��X�g�j����ł́A���߈ꉺ��70�ʂ��̌����҂̏����������W�߂邱�Ƃ͐��ȗ͂���������Ȃ�s�v�c�ł����ł��Ȃ����Ƃł��邪�A����Ƃ͍D�ΏƂ��Ȃ��A�V�����̑S�������̎s���ł���\���l��ɂƂ��āA����܂ʼn��̂������Ȃ��A���O����m��Ȃ������Ȋw�ҁE�����҂�������A���������{�S���݂̂Ȃ炸���E������A�{��O�����̍ő�̊댯���i�f�B�t�F���V���ϐ��ۏo���̊댯���j�ɂ��āA�x����炷���������玟�ւƓ͂���ꂽ���Ƃł���i�b86�`92�B94�B��118�`121�j�B�Ȃ��A�ނ�́A�����m��Ȃ���X�̍ٔ��̂��߂ɁA�ꕶ�̓��ɂ��Ȃ�Ȃ��ǂ��납�䂪�g�̌����ɕs���v�E��Q���y�Ԃł��낤���Ƃ����m�ł��̊댯���ڂ݂��A�����č���̍��ƓI�v���W�F�N�g�Ɉًc�̐����������̂��낤���\�\�v���ɁA�Ȋw�I�ȔF���Ƃ��āA�f�B�t�F���V���ϐ��ۏo���̉\�����s���̐l�̂̈��S�݂̂Ȃ炸�n����̐��Ԍn�ɋy�ڂ��e���̏d�含���l�����Ƃ��A�����҂Ƃ��Ď���̗����ƗǐS�ɏƂ炵�A�Ƃ��Ă��ق��Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ���������Ƃ����v���Ȃ��B
����ɑ��A�i�@�i���R�̍����ٔ����j�́A�{��O�����̊댯���ɂ��āA�����̌����҂ɕC�G���邾���̗����ƗǐS�������Đ����ɔ��f�ɗՂł��낤���B�����͈⊶�Ȃ��犮�S�ɔۂł���B���̌��ʁA���R�ٔ����́A���@23���̊w�⌤���̎��R�̖��̉��ɁA���̎��R�Ɖs���ՓˁE�Η�����u���N��j��邱�ƂȂ��A�܂���X�̐����̊�Ղł��鐶�Ԍn��j��邱�ƂȂ��A���N�ŕ����I�Ȑ������c�ތ����v�i���@25���A13���j���s���ɐN�Q����邱�Ƃ�e�F���A�n���̊��j��Ɏ��݂����݂̂Ȃ炸�A���ۑS�Ƃ̒��a�̒��ł����Ȋw�I�����̖����͂Ȃ����Ƃ�^���ɍl���Ă��鑽���̌����҂̐l�����ɐ[�����]��^�����i�ʎ�4�`8�̌����҂̊��z�Q�Ɓj�B�{���ʍR���́A���������ނ�Ɋ�]�����߂����߂̍ٔ��ł���B
4�A�{�ٔ��̎��
�{�ٔ��̎��͒P�������ł���B���Y�҂܂��͏���҂ł���\���l�炪�{��O�����ɑ��������{�I�ȋ^��Ƃ͈ȉ��̂悤�ɗv�邱�Ƃ��ł���B
�{��O�����ō͔|�����A�u�f�B�t�F���V���v���펞��ʂɎY�o����{GM�C�l�ɂ��āA
(1)�A���������ɁA�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��e�Ղɏo�����A�Ȃ����O���ɗ��o���đ�ʂɎ��ȑ��B����\��������ɂ�������炸�A����ɑ���S������Ă��Ȃ����ƁA
(2)�A�����H�i���S���̐R�����Ă��炸�A�E�ۍ܂ȂǂƓ��l�ɎE�ۍ�p�����u�f�B�t�F���V���v���ʂ��Đl�̂֊Q��p���Ȃ��̂��Ȃǂ̍�p�@�\�����𖾂ł��邱�ƁA
(3)�A���́u�f�B�t�F���V���v���i�P�ɁA������������ł͂Ȃ��j���悻�R���̐H�p�����ɂ͐�ɔ����܂��͈ڍs���Ȃ����ǂ��������𖾂ł��邱�ƁA
���̂悤�ȏŖ{��O���������s�������ʁA
(a)�A�o�������f�B�t�F���V���ϐ��ۂ�������̊O���ɗ��o���A���ȑ��B�����f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��A�l�̂̌��N�݂̂Ȃ炸�n����̐��Ԍn�ɏd�傩�[���ȉe�����y�ڂ����ꂪ����A
(b)�A���R���G�̉\���͑傢�ɂ��蓾��ȏ�A��q(2)�̈��S�����m�ۂ���Ȃ��{GM�C�l�����R���G��ʂ��Ĉ�ʐ��c�ɍL����A��ʕĂƍ��������{GM�Ă�����҂����ɂ���W�R���͍����A
(c)�A����ɂ́A���R���G��ʂ��Ĉ�ʐ��c�ɍL�������{GM�C�l��ʂ��āA�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ͂����ł��e�Ղɏo������\��������A�����Ȃ�����A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ͓d���ΉɎ���Ƃ���ɍL�܂邱�Ƃ͔������Ȃ��B
����ɑ��A�\���l�͂�����킸�ɂ͂���Ȃ��B
����҂ւ̌��N�A�������l���̕ۑS�A���ւ̈��e���̖h�~�𐭕{�̃o�C�I�e�N�m���W�[�헪�̍ŗD��ۑ�Ƃ��Čf���i�b51�j�A�܂��A�u�^�킵���͔�����v���|�Ƃ���\�h������GM�H�i�̈��S��������l���̕ۑS�Ɋւ��錴���Ƃ��Čf����킪���{�̉��Łi�b70�B��110�̕�����w�u�`�j�A
�\���s�\�� �Ɖs�\�� ��{���Ƃ���GM���̂������{���ɂ��āi�b108�j�A �{GM�C�l�Ɋւ��ă��X�N�i�댯�j�̂ݕ����A�x�l�t�b�g�i���v�j�͉������Ȃ����Y�҂܂��͏���҂ł���\���l�炪�A��̂����Ȃ闝�R�ł����āA��q�����悤�ɐl�̂̌��N���������A�������l���̕ۑS���낤�����A���Y�Ɗ��ւ̈��e�����m���Ɍ��O�����{GM�C�l�̖�O�����Ƃ����댯�ȏ�Ԃ���E���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���A�ƁB
5�A�{�ٔ��̑��_�𖾂ƌ��R�̐R���o��
(1)�A�O�q�̎����߂����āA�\���l�́A���R�̖`������A���_��4�ɍi���āA���̒ʂ�����i��������8�E11�j�B
�@�D ���R���G�̉\���ɂ��A����f�����Ō��ߎ�ƂȂ�u�C�l�̉ԕ��̌��G�\�͂̎��Ԃ͂ǂꂭ�炢���v�Ƃ����O������߂����āA������y�ш�R�ٔ����́A�{���Ȃ琶���w�I�Ȍ��n�ɗ��ׂ��Ƃ���A������u�l�H�v�I�Ȍ��n�Ǝ��Ⴆ��Ƃ����v���I�Ȍ��Ɋׂ��Ă���Ƃ������B
�A�D �f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���ɂ��A���̏o�������2�̘_���i�b82�A83�j����{��O�����ɂ����Ă��f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��o������\���͍����Ɛ������邱�Ƃ������I�ł���̂ɁA�����ے肷�鑊����y�ш�R�ٔ����̌����͌�������̂ł͂Ȃ����Ƃ������B
�B�D ��1�ɃR�}�c�i�R���̓�����`�q���A�J���V�i�R���ƋU���Ė{�������F�̐\�����s�Ȃ����_�ŁA��2�Ƀf�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���Ƃ��̉e���Ƃ����d��Ȗ��ɂ��ċL�ڂ�ӂ����_�ŏd��Ȏ葱�ᔽ�ł͂Ȃ����Ƃ������B
�C�D �\���s�\���Ɖs�\����{���Ƃ���GM���̂������{���ł́A���f��Ƃ��āu�^�킵���͔�����v�̗\�h�����̓K�p���K�v�s���ł͂Ȃ����Ƃ������B
(2)�A����ɑ��A�u�����ӔC��s�����v�ƕ\������������́A�����ׂ����ƂɁA�B�������āi���̔��_����10��4���܂ł��������j�A���R�̊ԁA���ЂƂ��_�������A�����т��āu�ق��Č�炸�v�̑ԓx��������B
(3)�A�����ŁA�{��O�����̈��S���ɂ��ēO��I�ȉ𖾂�]�ސ\���l�́A������̒��ق��u�\���l�̎咣��F�߂����́v�ƔF�߂Ă悢�����m�ɂ��邽�߂ɁA���R�ٔ����ɁA�����̑��_�Ɋւ��鑊����̔F�ہE���_��s�����悤�ɋ��߂��B
(4)�A������ɁA���R�ٔ����́A����ŁA��������炱���̑��_�ɑ��閾�m�ȔF�ہE���_����؏o����Ȃ������ɂ�������炸�A����ɂ��A������̊�ȂȒ��ق��u�\���l�̎咣��F�߂����́v�Ƃ͈��킸�A�����ŁA���R�ٔ������g���܂��A�\���l�����R�̊j�S�ł���ƒ��������̑��_�ɂ��āA������Ɠ��l�A�B�������āA�S�Ăɒ��ق��A�ЂƂ����f���Ȃ������B
�������A���ʂƂ��āA���R�ٔ����́A�\���l�̒������_�ɂ��A�\���l�̎咣�����ׂĔے肷��`�Ő\�������p���錋�_�����i�Ȃ��Ȃ�A�\���l�̎咣���m�肷��̂ł���A���R�̌��_���o�����Ƃ͕s�\������j�B�������A�\���l���������_���A�Œ���x�̗����ƗǐS�ł����āA���Ӑ[�����m�ɗ�����������A�\���l�̎咣��ے肷��ԓx���u�����ɂ܂������ł��邩�v���A��_�̋^�`���Ȃ����炩�ɂ���锤�ł���B�ȉ��A������ЂƂ����炩�ɂ���B
6�A�{GM�C�l�ƈ�ʃC�l�ƌ��G�̉\��
(1)�A���̏���
�C�l�̎��R���G�̉\���ɂ��Ĕ��f�����ŁA�u�C�l�̉ԕ��̌��G�\�͂̎��Ԃ͂ǂꂭ�炢���v�Ƃ����O����̔��f������I�ɏd�v�ł������B�Ȃ��Ȃ�A�{��O�����ō̂�ꂽ���G�h�~��́A�C�l�̉ԕ��̌��G�\�͂̎��Ԃ��u5�����v��O��ɍ��肳�ꂽ���̂ł����āA�\���l���咣����u50���ԁv�ł���Ί��S�ɔj�]������e����������ł���B
�����ŁA���̖����߂����āA���҂͐^��������Η����A���������u5�����v�𗠕t����؋��i�b112�A113�̌����҂̈ӌ����j����o����A��R�ٔ�����������̗p�����B �������A���̏؋��ɂ́A�v���I�Ȗ�肪�������\�\���̏؋����_���Ƃ��錤���_���͂�������A�����w�I�ɂ݂ăC�l�̉ԕ��͂ǂꂭ�炢�̎��ԁA���G�\�͂�L����̂���₤�����̂ł͂Ȃ��A�����ς�A�l�H�̌��n����݂Đl�H�ɓK����C�l�̉ԕ��͂ǂꂭ�炢�̎��Ԃ܂ł��A��₤�����̂���������ł���B�܂�A�l�H�ɓK����C�l�̉ԕ��̎������A�{��O�����̎��R���G�̉\���f���邽�߂ɗp���邱�Ƃ��Ȋw�I�ɐ��������Ƃ��B���ꂪ�����ł̑��_�ł���B
(2)�A���_�Ƃ��̗��R
���_�Ƃ��āA����͖��炩�ɊԈ���Ă���ƌ����ق��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���������A�{��O�����ɂ�����C�l�̎��R���G�̉\���̖��Ƃ́A�l�H���z�肷��悤�Ȑ����͂��錳�C�ȉԕ��Ɍ��肳�ꂸ�A�ǂ�ȂЎ�ȉԕ��ł��낤�Ƃ��A���₵�������G�\�͂����ێ����Ă�����̂Ȃ���������ׂđO��ɂ��āA��ʃC�l�Ƃ̌��G�̉\�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂�����ł���B�܂�A�����ɐ����w�I�ɂ݂āA�C�l�̌��G�\�͂��ǂꂭ�炢�̎��Ԃ���̂�����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂�����ł���B
����ɑ��A�l�H�ɂ����ẮA���̖ړI���炵�ē��R�̂��Ƃł��邪�A���C�Ő����͂���ԕ����������ƂȂ�A����䂦�A�l�H�ɂ�������G�\�͂̎��ԂƂ́A�u���C�Ő����͂���ԕ��̏�Ԃ́A�ǂꂭ�炢�̎��Ԃ��v�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B����䂦�A�A�����w���U���鐶�䕺�����̎w�E�i�b95�B13�ʼn�����7�s�ځj��҂܂ł��Ȃ��A���C�Ő����͂���ԕ��̏�ԂƂ��āA�u5�����v��������̂͐������B�������A���̌��_���A���悻���G�\�͂�ێ����邷�ׂẴC�l�̉ԕ��̎��Ԃɓ��Ă͂߂�̂́A���炩�ɊԈ���Ă���B
(3)�A���R�ٔ����̑Ή�
�ȏ�̗��R�́A��Âɐ������ΒN�ł���������x�̂��Ƃł���i�����炱���A����������ق��邵���Ȃ������̂ł���j�B�Ƃ��낪�A�����ɂ���́A���m�ɗ������邩�ۂ��ɂ���āA�{��O�����̊댯���̔��f�������ɂȂ��Ă��܂����̏d��Ȗ��ł���B�ɂ�������炸�A���R�ٔ����́A���̋ɂ߂ďd�v�Ș_�_�ɑ��āA�\���l���ڍׂ�s����������q���i�b95�j�Ɋ�Â�����Ԃ��咣�E�������ɂ�������炸�A�����ɉ��ЂƂG��邱�ƂȂ��A�P�ɁA �u�a���ɂ��A�C�l�̉ԕ��̌��G�\�͂�5�����x�ł���v�i3��9�s�ځj�Ƃ����F�肵���B�܂�A�\���l�����ꂾ���w�E�����ɂ�������炸�A���R�ٔ����́A�{��O�����ɂ�����C�l�̉ԕ��̌��G�\�͂̎��Ԃ́A�l�H�ōl����ԕ��̎����i5�����j�ōl��������Ƃ�����Ȋw�I�Ȋ��S�ɊԈ�������������Ă��܂����B���̌��ʁA�{��O�����̊댯���̔��f�ɂ��Ă��A�����̌��_���Ă��܂����̂ł���B
7�A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���Ƃ��̉e��
�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɂ��ẮA�����I�Ɏ���2�̑��_�����݂���B
(1)�A��R�ȗ��̘_�_�Ɋւ�����̏���
��R�ɂ����āA�\���l�́A���̂悤�Ɏ咣�����B�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���ɂ��A���̏o�������2�̘_���i�b82�A83�j����{��O�����ɂ����Ă��f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��o������\���͍����Ɛ������邱�Ƃ������I�ł���A�ƁB
����ɑ��A������́A��R�̃M���M���̍ŏI�i�K�Ɏ����āi���̂��߁A�\���l�ɂ͔��_����@��^�����Ȃ������j�A���̒ʂ蔽�_���Ă��āA��R�ٔ�����������̗p�����B
�b82��83�ŕ��ꂽ�����́A�ϐ��ۂ̐�����\�ɂ����邽�߁A���̐��������̊��e���̑��݂��Ȃ��A���悻���R�E�Ƃ͂������ꂽ�A����ȁA�l�H�I���̉��Ŏ������s�������̂ŁA���̎�������A���R�E�ŗe�ՂɁA�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��o������Ƃ����咣�̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ��i���c�q��2�ő�2�B��116�j�B�܂�A�b82��83�̎����́u���̐��������̊��e���̑��݂��Ȃ��v�����̏��������珉�߂đϐ��ۂ̏o�����\�������̂ł���A����ƈقȂ�A�u���̐��������̊��e���̑��݂���v���R�E�̏����ł́A���l�ɍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƁB
�������A���̂悤�Ȕ��_���Ȋw�I�ɂ݂Đ��������ǂ����B���ꂪ�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɊւ����1�̑��_�ł���B
(2)�A���_�Ƃ��̗��R
���_�Ƃ��āA���̔��_�͉Ȋw�I�ɂ݂Đ������Ƃ͌����Ȃ��B���̗��R�͈ȉ��ɏq�ׂ�ʂ�ł���B
�ؕ�ӌ����i�b99�B6��(�B)�j���w�E����悤�ɁA�u�a�b82��83�ɂ́A�ۂƃG�T�ƃf�B�t�F���V���������ĕ��u���邾���ŁA�ϐ��ۂ��o���Ə����Ă���̂ł�����A���R�E�ł����̎O�҂������荇���A�ϐ��ۂ��o�邾�낤�Ɨ\�z����̂������I�v�ł���A���̎O�҂������荇���������ɂ���{��O�������܂�����Ɠ��l�ɍl����ׂ�������ł���B
���������āA�ؕ�ӌ������w�E����ʂ�A�u���̗\�z��ے肷��ɂ́A�����ɋ��͂ȍ����������K�v�����v�i7��1�s�ځj�邪�A�ȉ��ɖ��炩�ɂ����ʂ�A������̔��_�͂��̐��_���ɑ����u�����ɋ��͂ȍ����v�ɂ͂قlj����B
���ɁA������́A�u���̐������̊��e���̑��݁v�̈Ⴂ���������邪�A�������A�ؕ�ӌ����i�b99�B6��(�@)�j���w�E����悤�ɁA�����Ƒ��̐����Ƃ̑��݊W�́u�r���I�ɓ����ꍇ�A��������ꍇ�A���̉e�����Ȃ��ꍇ�v�Ƒ��푽�l�ł����āA�������Ԃ̋����W�������̗Ⴊ����A����䂦�A�Ȋw�I�ɂ́A���̐����������݂��邱�Ƃ��A�ϐ��ۂ̏o���𑣐i����̂�����Ƃ��}������̂��͈�T�Ɍ����Ȃ��B
���ɁA������́A���̐������ȊO�̂��̂ɂ��āA���Ƃ��ł��T�^�I�Ȃ��̂Ƃ��āu�a�̊��e���̑��݁v�̈Ⴂ�A���Ȃ킿�u�������ł̐l�H�̉a�v�Ɓu���R�E�ł̉a�v�̈Ⴂ���������邪�A�������A�ؕ�ӌ����i�b99�B6��(�B)�j���w�E����悤�ɁA�ǂ��炪�u�ϐ��ۂ̏o���𑣐i���邩�v�͈�T�Ɍ����Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u�l�H�I�ȃG�T���������A���l�ȃG�T�����鎩�R�E�̕����A���l�ȋۂ����炵�āA�ϐ��ۏo���ɗL���ȏꍇ���o�Ă��邩��v�ł���A�܂��A��ʂɁA���c�y��1�O�������ɂ͐����Ȃ������\���ɋy�ԑ�ʂ̔����������݂ł��邭�炢�G�T�ɂȂ镨�������݂��Ă���A�ނ���{��O�����̐��c�̂ق����u�������ł̐l�H�̉a�v�����ϐ��ۏo���ɗL���ȏ�����������Ă���Ƃ������邩��ł���i����q��(3)5��2�s�ڈȉ��B�b91�j�B
��O�ɁA���������̎w�E�ł͂Ȃ����A�ؕ�ӌ����i�b99�B7��(�C)�j���w�E����悤�ɁA�b83�̎����ŁA�u�ˑR�ψٗU���܁i�G�`�����^���X���t�H���_�FEMS�j��p����Ƒϐ��ۂ̏o���p�x��8�{�ɂȂ����v�ƕ���Ă��邪�A�{��O�����̂悤�ȁu���R�E�v�ł��A���̓ˑR�ψٗU����EMS�ɕC�G����A�ˑR�ψق�U�����鋭�͂Ȃ��̂Ƃ��Ď��O�������݂���B���̂��߁A�i�ˑR�ψٗU���܂��g�p���Ȃ��j�u���������v���u��O�����v�̂ق����A�ނ���A�u�ϐ��ۂ̏o���𑣐i����v�ƌ������Ƃ��ł���B
�ȏ�̓��e���A�\���l�́A���R�ɂ����āA�ڍׂ�s�������ؕ�ӌ����i�b99�j�Ɋ�Â�����Ԃ��咣�E�������̂ł���B
(3)�A������̑Ή�
���̉Ȋw�I�Ș_�_�Ɋւ���\���l�̎咣�E���ɑ��āA�Ȋw�҂̐��ƏW�c�ł��鑊����́A���R�ɂ����Ĉꌾ�����_���Ȃ������B����́A��������g���\���l�̎咣��F�߂���Ȃ���������ɂق��Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���̌�A������́A�V���Ɏ��̘_�_���o���Ă��ď����ɒ���ł�������ł���B
(4)�A���R�̏I�ՂɎ���A��������V���Ɏ����o�����_�_�Ɋւ�����̏���
�\���l�̍R�����R��o��1�����ȏ�o�߂���9��27���Ɏ����āA������́A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��o������\�����Ȃ����R�Ƃ��āA�V���ɁA�u�Ȋw�I�Ɍ��m�v�Ȏ����Ə̂��āA �u�f�B�t�F���V�����C�l�̍זE����O���ɏo��\���͑��݂��Ȃ��v
�Ƃ������_�������o���Ɏ������i�������������(5)�B����ɁA����͉Ȋw�I�Ɍ��m������A����16�N11���̎������F�̐\���葱�̂Ƃ��ɂ����͂Ȃ������Ǝ咣���邪�A����قǂ܂łɉȊw�I�Ɍ��m�ƌ����̂Ȃ�A�ǂ����āA�{�������\������3�������o�߂������R�̍ŏI�i�K�Ɏ����ď��߂āA������咣����Ɏ������̂��A����s�\�ł���j�B
�������A���̂悤�Ȕ��_���Ȋw�I�ɂ݂Đ��������ǂ����B���ꂪ�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɊւ����2�̑��_�ł���B
(5)�A���_�Ƃ��̗��R
���_�Ƃ��āA���̔��_�͉Ȋw�I�ɂ݂āA�Ƃ������Ȋw�ȑO�̏����I�Ȓm���̃��x���Ō�����m��Ȏ咣�Ƃ����ق��Ȃ��B���̗��R�͈ȉ��ɏq�ׂ�ʂ�ł���B
�A�A������́A�f�B�t�F���V�����C�l�̍זE����O���ɏo�Ȃ����R�̂ЂƂƂ��āA�u�A���̍זE�ǂ̍\���I�ȓ����v��������B�܂�A�זE���m���Ȃ��ׂ��ʘH�i�v���X���f�X�������`���A���j�̒��a��20�`40�i�m���[�^�[�ł���A������ʉ߂ł��镨���̑傫���͕��q�ʂɊ��Z����800�ȉ��̃T�C�Y�ł���Ƃ���A�J���V�i�f�B�t�F���V���̕��q�ʂ͖�5�A700�ł����āA�u�傫�����ād�d���̒ʘH���I�ɒʉ߂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��v�A�Ɓi��������(5)7��(6)�j�B �������A����͉Ȋw�ȑO�̏����I�Ȓm���̃��x���œ�d�Ɍ���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A��1�ɁA�f�B�t�F���V�����זE���m���Ȃ��v���X���f�X����ʉ߂����Ƃ���ŁA�����܂ł��ׂ̍זE���̓����Ɉړ����邾���ł����āA������Ȃ�ׂ�Ԃ����Ƃ���ōזE���̊O�ɏo��킯�ł͂Ȃ��A�����������̋c�_���̂�����������ł���B
��2�ɁA���q�ʖ�5�A700�̃J���V�i�f�B�t�F���V���̒��a�́A��2�`4�i�m���[�^�[�ł���i���q�ʂ��قړ����C���V�������̒��a���������ʎ�1�}�ʎQ�Ɓj�A���a��20�`40�i�m���[�^�[�̃v���X���f�X�����炭�炭�ʉ߂ł��邩��ł���B
�C�A������́A�f�B�t�F���V�����C�l�̍זE����O���ɏo�Ȃ����R��2�ڂƂ��āA�u�f�B�t�F���V���ƃ}�C�i�X�ɉדd�����זE�ǂƂ̃g���b�v�i�����j�v��������B�܂�A �u�f�B�t�F���V���́A�E�E����̒`�����ł���A�E�E�}�C�i�X�ɉדd�����זE�ǂƌ����v���A�𗣂��Ȃ��A�Ɓi6�y�[�W(2)(5)�j�B
�������A������܂��A�Ȋw�I�Ɍ��m�ȃ��x���Ŋ��S�ȊԈႢ�ł���B�Ȃ��Ȃ�A����ӌ����i�b125�B3��b�j���w�E����ʂ�A�u����͉Ȋw�I�Ɍ��m�Ȏ����ł����A���c�̐��ɂ�Ca2�{�AMg2�{�ANa�{�A�@K�{�ȂǁA�}�C�i�X�̉דd�𒆘a����C�I�����\���ɑ��݂���̂ŁA�����̃C�I���ōזE�ǂ̉דd�����a����A���������f�B�t�F���V�����e�Ղɉ𗣂��A�n�o���邩��ł��B�v
�E�A�����āA�u�f�B�t�F���V�����C�l�̍זE����O���ɏo��\���v�ɂ��Č����A�Ȋw�I�Ɍ��m�Ȏ��̗��R�ɂ�蓖�R�m��ł���B
(�@)�A���������f�B�t�F���V���́u����^����ς����v�ł���A���召�E�ɉ^��āA�זE������זE���̊O�ɕ��o�����i�ʎ�2�}�ʎQ�Ɓj�B
(�A)�A�זE���̊O�ɕ��o���ꂽ�f�B�t�F���V���́A20�`40�i�m���[�^�[�̃v���X���f�X�����ʂ�邾�����ď�̍זE�ǂ̊Ԃ��炭�炭�ʉ߂ł���i�ʎ�3�}�ʎQ�Ɓj�B
(�B)�A���Ƃ��A�f�B�t�F���V�����}�C�i�X�ɉדd�����זE�ǂƌ��������Ƃ��Ă��A�C�őO�q�����ʂ�A���c�̐��Ƀ}�C�i�X�̉דd�𒆘a����C�I�����\���ɑ��݂��邽�߁A�זE�ǂ̉דd�����a����A���������f�B�t�F���V���͗e�Ղɉ𗣂���B
(6)�A�ȏォ��A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ��e�Ղɏo������\���͍����ƌ��킴����A�����Łu�^�킵���͔�����v���|�Ƃ���\�h�����ɏ]���A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɑ���s���Ƃ����ׂ��ł���B
������ɁA���R�ٔ����́A�{�ٔ��̍ŏd�v�̂��̘_�_�ɂ��āA�S�������̓I�Ȍ��y�����邱�ƂȂ��A�ɂ�������炸�A�\���l�y�є������̐��Ƃ����̈ӌ�����]���āu�X�J�v�ɂ����Ȃ��ƒf�����i3�Łj�B�u�a�����Ȃ��v�Ƃ�������Ȃ�������R�̌���ƈقȂ�A�u�X�J�ł���v�Ƃ܂ŕ\�������ȏ�A��قǂ̉Ȋw��̊m�M�Ɏx����ꂽ���̂Ǝv���邪�A����Ȃ�A�O�q�����Ȋw�ȑO�̏����I�Ȓm���̃��x���ł���ԈႢ�Ɋׂ��Ă��鑊����̓m��Ȏ咣����̂ǂ̂悤�ɗ��������̂��낤���B
8�A��O�������F�̂��߂̐\���i�K�ɂ�����d��Ȏ葱�ᔽ
(1)�A�R�}�c�i�R���̓�����`�q���A�J���V�i�R���ƋU���Ė{�������F�̐\�����s�Ȃ����_ �A�A���̏���
�\���l�́A�{�������F�̐\���葱�ɂ��āA�u�{���Ȃ�A���F�\�����i�a�b21�B�ȉ��A�{�\�����Ƃ����j�Ƀf�B�t�F���V����`�q���R�}�c�i�R���Ə����ׂ��Ƃ���A����Ƃ͕ʎ�̐A���ł���J���V�i�R���ƋL�ڂ��āA�{��O�����̏��F�����_�v����Ƃ��A��`�q�g���������̈��S���R���ɂ����čł���{�I�ŏd�v�Ȏ����ł���w����������`�q�x�Ɋւ��鋕�U�̋L�ڂƂ��āA���̏d�含���w�E�����B
����ɑ��A���R�ٔ����́A
�@�D�܂��A�u���F�\�����ɁA�f�B�t�F���V����`�q���R�}�c�i�R���Ə����ׂ��Ƃ���A�J���V�i�R���ƋL�ڂ��āA�{��O�����̏��F�����v�i4��4�s�ځj������F�߂����̂́A
�A�D���̈�@���̕]���ɂ��ẮA���̋��U�̋L�ڂ̎����́u�⊶�ł���Ƃ����ׂ��ł��邪�A�{����O�������F�葱�ɏd������r������Ƃ͕]���ł��Ȃ��v�ƁA�Ȃ��d������r�łȂ��̂��ꌾ�����R�𖾂炩�ɂ��邱�ƂȂ����_���������B �������A���̋��U�̋L�ڂ��d������r�ł͂Ȃ��Ƃ����邩�ǂ����B���ꂪ�����ł̖��ł���B �C�A���_�Ƃ��̗��R
���_�Ƃ��āA����͏d������r�ƌ��킴��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���Ƃ������A�u���i�Ȃ̐A���Ƃ͂����A�R�}�c�i�ƃJ���V�i�ł͂��̈�`�q�̔z��͈قȂ�A����䂦�A�R�}�c�i�ƃJ���V�i�̃f�B�t�F���V���ł́A�������a�ۓ��ɑ����p���قȂ�B���������āA��`�q�g���������̈��S���̊m�F�ɂ��Ă��A���ꂼ��ʌƗ��Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł����āA�����A�u���i�Ȃ̐A��������A�ǂ���ł����������Ⴂ�͂Ȃ��ƕ]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���i���ɁA�����̓����ł��A��p���قȂ�ΕʁX�ɕی삳��Ă���A�ʁX�̕]�����Ă���j�B
(2)�A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���Ƃ��̉e���Ƃ����d��Ȗ��ɂ��ċL�ڂ�ӂ����_
���R�ٔ����́A�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���Ƃ��̉e���Ɋւ���\���l�̎咣�́u�X�J�v�ɂ����Ȃ��ƕ]�������̂ŁA���F�\�����ɂ�����L�ڂ��Ȃ��Ă��u�����@�Ƃ͂����Ȃ��v�Ƃ����i4�Łj�B�m���Ɏ����т��Ă���B�������A�O�q�����ʂ�A���̑�O�S���̊ԈႢ�ł���ȏ�A���̎葱�ᔽ�̖����ˑR�d�v�Ȗ��Ƃ��Ė���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
9�A���f��Ƃ��Ắu�\�h�����v�̕K�v��
(1)�A�\���l�́A�`���I�Ȏ��̘̂g���Ɏ��܂��Ȃ��\���s�\���Ɖs�\����{���Ƃ���GM���̂̓����ɂ��݁A�{GM�C�l�̖�O�����̊댯����K�ɔ��f���邽�߂ɂ͂��̔��f��Ƃ��āA����GM�H�i�̈��S��������l���̕ۑS�Ɋւ��錴���Ƃ��Ċm�����Ă���\�h�������̗p���ׂ��ł���ƁA���Ȃ킿�u�V�������͐V�����v�܂ɐ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƈ�R�ȗ������т��Ď咣���Ă����B
(2)�A������ɁA���R����́A����ɑ��锻�f����ؖ��炩�ɂ��邱�ƂȂ��A�Ȃ������ʓI�ɗ\�h�����̓K�p��^��������ے肷��ԓx�ɏo���B�Ȃ��Ȃ�A���Q�̗\�����s�\�Ȃ̂�GM���̂̓����ł���ɂ�������炸�A�u�{����O�����ɂ���āA�d�d�R���l�R�c��̔_�n���Ƀf�B�t�F���V���ϐ��ۂ���������Ȃǂ��đ���̑��Q��^���邨���ꂪ����Ƃ̑a���͂Ȃ��v�u����҂̍R���l���o��ɖ��m����̓I�ȑ��Q����������W�R���������Ƃ̑a�����S���Ȃ��v�i4��6�j�Ɣ��f��������ł���B
(3)�A�������A���̑ԓx�́A�{���ŗ\���s�\���Ɖs�\����{���Ƃ���GM���̂̊댯���Ƃ������m�̐[���Ȗ�肪�s������Ă���ɂ�������炸�A����ɑ���K�Ȕ��f��͂ǂ�����ׂ����ɂ��ĉ���ᖡ���邱�Ƃ��Ȃ��A�����P�ɋ��ԈˑR����`���I�Ȏ��̂̔��f��ő����Ƃ������̂ł���A���̌��ʁA����́A��L(1)�y�шȉ��Ɏ����ʂ�AGM���̂ɂ����鐶�����Ɗw�⌤���̎��R�Ƃ̐l�����݂̏Փ˂̒����̔��f�����������@�ᔽ�ƌ��킴��Ȃ��B
�A�A�u�^�킵���͔�����v���|�Ƃ���\�h�����o��̕K�v��
�u�^���v�Ɋւ��邱��܂ł̓`���I�Ȗ@�������́u�^�킵���͔������v�ł������B�ł́A�ߎ��AGM�H�i�̈��S��������l���̕ۑS�Ɋւ��錴���Ƃ��āA����Ɛ^���ʂ���Η�����悤�ȁu�^�킵���͔�����v���|�Ƃ���\�h�������Ȃ��o�ꂷ��Ɏ������̂��B ����́A�ߎ��A�`���I�Ȏ��̘̂g�g�݂ɂ͎��܂��Ȃ��u�V�������́v���o������Ɏ���������ł���B�Ȃ��Ȃ�A���́u�V�������́v�͓`���I�Ȏ��̂ɂ͂Ȃ���������4�̐V���������B
�@ ���X�N�̕s�m�����B
�A �s�t���B
�B �Ӕ����i���Ƃ��A�a���̂�̓��Ɏ�荞��ł�����ۂ̔�Q����������܂łɎ��Ԃ������邱�Ɓj�B
�C �z�����i���X�N�����������Ĉړ����邱�Ɓj�i�b108�B99�Łj
�����ŁA���̐V���������[���Ȏ��ԂɓK�������K�ȑΏ����@�͂ǂ�����ׂ��������ꂽ�B���̋ᖡ�̖��Ɍ��o���ꂽ���̂��ق��Ȃ�ʂ��̗\�h�����ł������B
�����āA����4�̐V�������͂���̂̓T�^�̂ЂƂ�GM���̂ł���i��������(11)16�ŁB�b108�B99�Łj�B
���̗\�h�����́A���ۊW�ł͊��ɐ������̏��A����ɓK�p����Ă���i�b108�B100�Łj�A�{���ɂ��W���镨���l�����i1993�N�j�A�J���^�w�i�c�菑�i2000�N�j�ɂ����ꂪ�܂܂�Ă���B
�C�A�\�h�����̓��e
�ł́A����͂ǂ�ȓ��e�������̂��B�V�����o�ꂷ�錴���̏�Ƃ��āA���̓��e�͖��������r��ɂ���B�������A���Ȃ��Ƃ��A���̍ł��d�v�ȓ��e�Ƃ��āA�u���ؐӔC�̓]�������S���̗��ؐӔC�͊J�����鑤�ɂ���v���������i�b108�B101�Łj�A����͊��ɁA�X�E�F�[�f����p���ł́A���L����Ă���i�b44�u�\�h�����v242�Łj�B
(4)�A����
�{�����܂��A�{��O�����̈��S���̗��ؐӔC�͎��������{���鑊����ɂ���Ƃ����ׂ��ł���A�������Ƃ���A����܂ł̖{�ٔ��̐R�����e���炵�āA��������u�{��O�����̈��S����a�������v�Ƃ͓��ꌾ���Ȃ����Ƃ����X���X�ł���B
10�A�R���̎�|�ύX�̉ۂɂ���
(1)�A���R�ɂ����āA�\���l��8��25���ɍR�����R�𖾂炩�ɂ����ɂ�������炸�A����ɑ��A��������A�Y���Y����1�����ȏ㉽�̔��_����o�����A�ٔ������܂��A�\���l�̍ĎO�Ďl�̐R�����i�̏�\�ɂ�������炸�A������̌̈ӂƂ��������悤�̂Ȃ��i�גx���s�ׂ��ɂ߂Ċ���ȑԓx�ŗe�F�������߁A���̌��ʁA���R�ٔ����̔��f���n���Ȃ������ɁA10��3���A�{GM�C�l�̊����肪���s����Ă��܂����B�����ŁA�\���l�́A�{GM�C�l�̊�����̎��Ԃ�z�肵�āA���̖�2�T�ԑO����A�{�ٔ��̍ő�̘_�_�ł���f�B�t�F���V���ϐ��ۏo���̊댯���ɑΏ����邽�߂ɉ������\����ύX����|�ٔ����ɗ\�����A���̌�ɍR���̎�|�ύX�̐\�����s�Ȃ����B������ɁA���R�ٔ����́A�ȉ��ɖ��炩�ɂ���悤�ɑi�葱�㉽���肪�Ȃ��\���l�̍R���̎�|�ύX�̐\�����A�c�E�����Ƃ��������悤�̂Ȃ��e�ȑԓx�őΉ����A�����F�߂Ȃ������B�������A����͑i�葱������炩�ɊԈ���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�{�������ٔ��ɂ����āA�i���̕ύX�̋K�肪���p�����ȏ�A���Ƃ��ƁA
�@�D �����̊�b�ɕύX���Ȃ����Ɓi�R���̊�b���Ȃ������������V�E�����i�̊Ԃň�����x���ꐫ�������Ɓj
�A�D �������i�葱��x�������Ȃ�����
�������������A�R���̎�|�ύX���F�߂���i���i�@143���j�B
�Ƃ���ŁA�{���́A�O�L�@�ɂ��A�{��|�̕ύX�ɂ��A�]���A�\���l���咣�E�����Ă����������������p�ɂȂ邱�Ƃ�1���Ȃ��A�܂��V���ɐ\���l���咣�E�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�Ȃ��̂�1���Ȃ��B���Ȃ킿�A�]�O�̎咣�E���ɉ�����炵�������������A�������肻�̂܂܂ŐV������|�̔��f���ł���B
�Ȃ��Ȃ�A�ύX��̎�|��(3)�ł���u���N�x�̎����̒��~�v�ɂ��ẮA���Ƃ��Ƒ�����́A�{��O�����̏��F�\�����ɁA�{�N�x�݂̂Ȃ炸���N�x�̎������Z�b�g�Ő\�����Ă���A���̎������e������ł��邱�Ƃ͑�������g�̐\�����i�b21��1�Łj�A�͔|�����v�揑�i�b8�j�Ŗ��炩������ł���B�܂��A�ύX��̎�|��(1)��(2)�ł���u�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̎E�ۍs�ׁv�ɂ��Ă��A�]���A�\���l�����͂Ɏ咣���Ă����f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̏o���̉\�������m�肳���A���������h�~������K�v���͒����ɖ��X���X������ł���B���ɁA��R�ł��A�����ʂ�u�R������l�߂ɋ߂Â����v8��3���A�\���̎�|���A�{GM�C�l�́u��t���֎~�v����u�����肹��v�ɕύX�������A���Ȃ��A�F�߂�ꂽ�B
����䂦�A�O�L�A�ɂ��Ă��A�{��|�̕ύX�ɂ��i�גx���̖��͉�������Ȃ��B�����{�ٔ��ɂ����đi�גx�����������Ƃ�����A����͂ЂƂ��ɁA��R�ɂ����āA���ُ���o��1�����ȏ����v���_�ɂ��ď��ʂ���ؒ�o���Ȃ�������������A���R�ɂ����Ă��A8��25����o�̐\���l�̍R�����R�ɑ��āA1�����ȏ㔽�_���o���Ȃ������Ƃ����A�����̐ŋ����g���A�����I�v���W�F�N�g�𐋍s���闧��㍑���ɓO�ꂵ�������J�Ɛ����ӔC�����̑�����́A���̐ӔC����������O�ꂵ���葱�I�s���`���ɂ���B
(2)�A����ɁA���R����́A�u�R���l��́A�{�����R�̐R������l�߂ɋ߂Â�������17�N10��4���Ɏ����āA�ˑR�ɍR���̎�|��ύX����Ǝ咣�����v�ƔF�肷�邪�A����͖��炩�ɂ��������B
�Ȃ��Ȃ�A��1�ɁA�\���l�́A9��22���ɑ��X�ƁA�u�i�s�Ɋւ����\���v�̒��ŁA���̒ʂ�A��|�ύX�̗\���m�ɂ��Ă���A���R���肪�F�肷��悤�ȁu�ˑR�Ɂv�ł͑S���Ȃ�����ł���B
�s�\���l�́A�����A�uGM�C�l��������v�Ƃ����\���Ă̎�|�Ƃ̊W�ŁA�{GM�C�l�̊�����̗L�����莋���Ă��܂������A���ʁA�f�B�t�F���V���ϐ��ۂ̐��ƂƂ̋��c�̌��ʁA�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɊւ���h�~��̕K�v�́A�{GM�C�l�̊�����̗L���Ƃ͊�{�I�ɊW���Ȃ����Ƃ��������܂����̂ŁA�{GM�C�l�̊�����̗L���Ɋւ�炸�A���R�̐R����i�߂Ă��������A�ł��邾�������̔��f�����肢�������ƍl���܂��B
�����Ƃ��A�\���l���A�ߓ����ɁA�u�f�B�t�F���V���ϐ��ۂɊւ���h�~��v�ɑ��������\���Ă̎�|�̕ύX���o����\��ł��B�t�i3�Łj
��2�ɁA9��26���A���������悤�₭���R�ɂ����锽�_���o���ꂽ�̂��āA�\���l�́A9��30���t�Łu�i�s�Ɋւ����\���v�̒��ŁA
�s������̍���̔��_�̌����ȓ����́A�\���l������Ԃ����炩�ɂ������̊j�S�����ɑ��āA��A�ق��Č�炸�Ƃ����ԓx��O�ꂳ�����d�d��͂�A�����{�����̊j�S�����ɂ��ẮA�����Ȃ��ŁA�\���l�̎咣�ɑ��鑊������g�̌�����������ƕ\�����Ă��炢�����Ǝv���܂��B�t�i2�Łj
�Ƃ����܂ł�������̐ϋɓI�Ȕ��_�̒�o�����߁A�Ȃ����A
�s���T���X��o�̐\���l�̔��_�ɂ��A�{���̖��_�̊j�S���M�ٔ����ɂ����Ȃ薾�炩�ɂȂ�Ǝv���܂����A�����Ɂi���̎�̐��I�����̏�ł����j�O�������m���Ɋւ���^��_�A�s���_���܂����߂Ė��炩�ɂȂ�Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŁA���_�����݂̂Ȃ炸�O����E���m���Ɋւ���^��_�A�s���_�̉𖾂̂��߂ɁA����Ƃ��A�Z�p������̑����J�Â�v�]�������܂��B���̓_�A��������ًc���Ȃ��|��\�����Ă���i��������(5)10�Łj�A��X�Ƃ��ẮA�K�v�Ȑ��Ƃɂ����Ȃ��Ă��炢�A�O����E���m���Ɋւ���^��_��O��I�ɉ𖾂��Ă��������Ɗ���Ă���܂��B�t�i1�`2�Łj
�ƐR�����悤�₭���O����}���A���ꂩ�瑈�_���ϋl�߂邽�߂̓O�ꂵ���c�_�����킷���ł͂������̂ł���A���R���F�肷��悤�ȁu�R������l�߂ɋ߂Â����v�킯�ł͑S���Ȃ�����ł���B
(3)�A����
�ȏ�A�����t��ƌ����ق��Ȃ������F��ɂ���|�ύX��F�߂Ȃ��������R�ٔ����́A�葱�I�s���`���̌����s������������̌�ǂ������Ă�����̂ƕ]����Ă��d���Ȃ��A���̌��ʁA�\���l��̍ٔ����錠���i���@32���j�͒������N�Q���ꂽ�B
11�A�I���Ɂ\�\�������܂ꂴ��҂����ɑ���`���̗��s�\�\
�\���l��́A�{���ʂ̖`���ŁA�s�{���ł́A�u�l�Ԃ̗��j��O��̂Ȃ��Z�p��̗͋Ɓv�ł����`�q�g�����Z�p�Ƃ����l�דI�ȑ���ɂ��A�d�d�l�ԎЉ�̍������Ȃ��ŏd�v�Ȑ������Ɗw�⌤���̎��R�Ƃ����l�����݂̍ł��[���ȏՓ˂̒���������āt����Ə������i4�Łj�B �������AGM���̂̓����̂ЂƂł���u�Ӕ����v �Ɏv����v�����Ƃ��A�{���̍ő�̔�Q�҂͎��͐\���l�����ł͂Ȃ����낤�Ǝv�킴��Ȃ��B�{���̍ő�̔�Q�҂́A���炭�������̎q���A�������A�����Ė������܂ꂴ�鎄�����̎q�������ɂ������Ȃ��B�������AGM���̂̂����ЂƂ̓����ł���u�s�\���v�Ɏv����v�����Ƃ��A�ނ炪�~�ς����߂Đ\���l�ɂȂ낤�Ƃ����Ƃ��ɂ͂����x���̂ł���B���̈Ӗ��ŁA�\���l��́A�������̎q�������A�������܂ꂴ�鎄�����̎q�������ɑ����đ�\���Ă��̍ٔ����s�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B����䂦�A����͒P�Ȃ鎄���ƍ��ƓI�v���W�F�N�g�Ə̂���{��O�����̊Ԃ̖��ł͂Ȃ��B���̖{���́A�������̎q�������A�������܂ꂴ�鎄�����̎q�������̐l���ƍ��ƓI�v���W�F�N�g�̊Ԃ̖��ɂق��Ȃ�Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA�䂪������GM�앨���߂���{�ٔ�����21���I�̗ϗ����ł��s�������ł��p�u���b�N�ȍٔ��ł���B
�ȏ�
�ʎ��̊T�v
�ʎ�1�}�ʁFTrudy McKee�ق��u�}�b�L�[�����w�i��3�Łj�v100��
��2�}�ʁF����41��
��3�}�ʁFBruce Alberts�ق��u�זE�̕��q�����w�i��4�Łj�v1120��
��4�F�R�`��w���w�������������w�ȋ��� ���c�Y�O�쐬�i�b94�A116�̍쐬�ҁj
��5�F�O�}�g��w�_�w������ ���䕺���쐬�i�b95�̍쐬�ҁj
��6�F������w�C�m���������� �ؕ��[�쐬�i�b99�̍쐬�ҁj
��7�F�Y�ƋZ�p���������� �����@�\�H�w���������C������ ����M���쐬�i�b19�A80�A91�̍쐬�ҁj
��8�F�Y�ƋZ�p���������� �����@�\�H�w�������� ������ ���R�N�u�쐬�i�b87�̍쐬�ҁj
(2005/11/11)